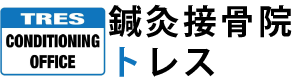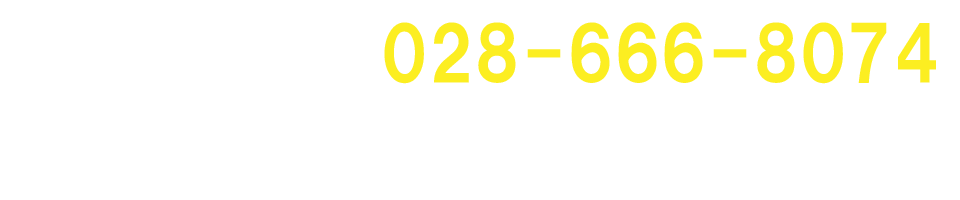鍼灸接骨院トレスのブログ

施術について , 症例報告 , 膝痛
2018年07月15日

宇都宮市JR岡本駅より徒歩5分。
可動域向上・動作改善・強化による症状の根本改善を目指した施術とパーソナルトレーニングを提供している鍼灸接骨院トレスです。
年齢とともに擦り減ってしまう膝の軟骨や半月板。
膝が痛くて病院に行くと先生に「年だから仕方ない」と言われ、憤って来院される方もいらっしゃいます。
不平や不満を愚痴ってもらってそれを聞くのも我々の仕事ですので全然構いませんが、経験上、愚痴からは何も生まれないので何をすべきか前向きに考えましょう笑。
ということで、膝の調子が悪くてウォーキングを始める方が多くいらっしゃいますが、場合によってはエアロバイクやサイクリング、または軽いスクワットの方が良いですよ?ということをご紹介したいと思います。
多くの女性が悩まされる膝の痛み
一般的に年齢的な膝の痛みは女性に多いと言われています。
学生時代に変形性膝関節症の7割~8割は女性に起こる、と教わった記憶があります。
なんでも閉経後のホルモンの関係で起こりやすいため、女性に多いんだとか。
でも、実際のところ7割8割の女性に起こると言われていても、症状として現れない人もカウントされているので、人によっては酷い変形を起こして痛んだりする人もいれば、検査すると変形が疑われるけど見た感じ変形していないし痛くもない、と言う人もいるのが実際です。(見た目変形しているけど痛くない、という猛者もいらっしゃいますが)
症状として出る出ないに関わらず、女性にとって弱い部分であることに変わりないので、日頃から対策をしておきたいところです。
実際のところ、何の運動が良いの?
症状が出ていない人や、比較的症状の軽い人はウォーキングしていただくのがベストかと思います。
基本的に当院の指導は「歩けるなら歩け」というスタンスですので、地面からの衝撃に耐えられるのであれば、その刺激は骨も丈夫にしますので、膝以外の部分に良い影響をもたらす可能性があり歩くのがベストです(閉経後の骨粗しょう症対策にも)。
上記ような方は、基本的に治療にいらっしゃることは少ないので、予防として、日頃の運動として取り入れていただくと良いかと思います。
一方で、治療を受けにくる変形や痛みがひどく歩くことが辛い、と言う方に対しては積極的なウォーキングは勧めていません(症状が良くなってから歩けばよい、という考えのもと)。
そのような方にはエアロバイクをお勧めします。
変形が酷い方の場合、ペダルの下死点(時計で言う6時の部分)になると膝が伸びきらずに痛みを感じる、と言う方もいらっしゃいますが、その場合はサドルを低く下げてもらっています。
スポーツとしてのサイクリングであればサドルを上げて上体を前傾してお尻の筋肉を使って…、と言ってしまいがちですが、ここではあくまで膝のリハビリ・トレーニングとしての内容なので痛くないところまで下げてもらっています。
また、軽いスクワットもお勧めです。
ただし、スクワットの場合も股関節の動きを伴った正しい方法を取らないと逆に膝に負担がかかりますので注意が必要です。
当院で膝のトレーニングとしてスクワットをやっていただく場合、スクワットの動作を正しく行えるようなトレーニングを先に処方してからスクワットの指導に入ります。(スクワットトレーニングをするためのトレーニングが必要)
また、最近導入したMCC(マルチカフケア)という加圧してトレーニングを行う器具を使ってスクワットすることで、より効率的に早く筋力を戻していく事が可能になりました。
こちらも当院の患者さんにはチャレンジしてもらっていますので、お悩みの方はご相談ください。
動かすことの重要性
軟骨や半月板自体、血流が乏しい部分ではあります。
それゆえ、一度損傷してしまうと再生しないとか、治りにくいとも言われています。
再生医療が進歩すればそれすら解決してしまうと予想されていますが、いつ使えるか分からないそれを待っているだけではよろしくないので、まずは動かすことを念頭に考えておきたいところです。
動かす重要性は、関節内部の構造にはスポンジの様のものがあり、そこから潤滑油のような物質が出てくることにあります。
水を染み込ませたスポンジを思い浮かべてもらえれば理解しやすいと思いますが、スポンジを絞れば水がジュワっと出てきますね?
関節も一緒で動かすことで潤滑油がジュワっと出てきます。
動き始めだけ痛かったり違和感を感じる場合には、動かしたことで潤滑油が回り滑らかに動くようになることで症状が軽減するといったメカニズムが起きています。
機械も壊れないように適度に油を注すように、関節に油が回って滑らかに動いていれば摩擦が起きにくく壊れにくくなります。
そんなことから適度に動かすことが重要であり、その時の状況に合わせた最善の負荷をかける必要があります。
リハビリとしてスクワットを取り入れたいならご相談を
エアロバイクはジムに行くか、自宅に設置しなければできませんので、スクワットで何とかしたい方もいらっしゃると思います。
日頃から知識を持って筋トレをしている人でない限り、正しくスクワットができる人はそうそういません。
多くは膝に負担をかけるやり方であったり、どこに効いているのか分からないやりかたであったり。
良く言われる「爪先より膝が前に出ないように」というものも、なぜそうなのか?膝を前に出さないとしゃがめない?膝は前に出てないけど何かおかしい?といった疑問や問題も出てくると思います。
その辺の問題を解決するためにも「スクワットトレーニングするためのトレーニング」が必要であったりしますので、自己流で間違った負荷をかけて悪化させてしまう前にご相談いただければと思います。
投球障害肩 , 施術について , 野球肘
2018年07月10日

宇都宮市JR岡本駅から徒歩5分。
可動域向上・動作改善・強化による症状の根本改善を目指した施術とパーソナルトレーニングを提供している鍼灸接骨院トレスです。
今回のケースは野球肩や野球肘の診断を受けて投球制限(または禁止)を一定期間おこない復帰したものの、また同じ場所に痛みが出てきてしまったものの話。
思い起こせば、私自身も高校球児時代はこの繰り返しだったような気がします。
野球も昔と違って球数制限や分業制が一般的になって来ていますが、それでも痛めてしまう選手が少なくありません。
繰り返してしまっている場合には今までとは別なアプローチを考える必要性が出てきますが、初めて痛くなってしまった場合には最初のアプローチがその後の選手生命を左右しかねません。
私自身も苦しんだところですので、これからの選手たちには同じような思いはして欲しくないと常々思っています。
野球に限らず、とくにオーバーユーズで起こるスポーツ障害でお悩みの方が、どういう考えを持つべきか参考になればと思います。
復帰するまでの過程
おそらくスポーツ障害で治療院に来る方の多くは「痛みが治まれば復帰できる」と思っている方が少なくないのではないでしょうか?
ここは大きな間違いで、スポーツで復帰をする場合には「痛みなくプレーできること」以外に「競技中の負荷に耐えられるようになっているか」というところが重要です。
この「競技中の負荷に耐えられる」というのは、筋力的な回復はもちろん、繰り返しの動作をおこなっても大丈夫な機能的な動きを獲得できているかどうか、というところになります。
痛みが止まっても、筋力も回復していなければ耐え切れないのは想像に難しくないと思いますし、痛めた原因となる「悪い動かし方」が残っていれば、動かした時にまた同じところに負荷をかけ続けることになります。
ということで、復帰までの過程は治療する期間とリハビリ等でトレーニングをする期間が必要になります。
当院の治療方針で「可動域向上・動作改善・強化」を提唱している理由がここにあります。
治療期間
一般的に組織が損傷すると治るまでに一定の期間が必要になります。
例に挙げると、皮膚の損傷で1週間程度、軽い肉離れで2~3週、酷い肉離れで2ヵ月、靭帯の軽度損傷で2ヵ月、重度損傷で6ヵ月、と言われています。
この期間において、患部に対して当院では鍼治療、物理療法、マッサージなどの手技療法などをメインに行います。
また、最初の段階(初診時)で患部に負担をかけうる動作不良を確認しているので、そこに対するアプローチも行います。
動作不良に関して言えば、患部以外のところの問題が多いため、治療期間から積極的にアプローチしています。
例えば肩の痛みが股関節や胸椎に問題があった場合、この段階では肩のトレーニングはしないけど、股関節や胸椎のトレーニングはおこなう、といったところです。
トレーニング期間(リハビリ期間)
当院では先に述べたとおり、治療期間中に動作不良へのアプローチを進めていますので、痛みの軽減を待ってからリハビリを行うよりも総合的な治癒期間は短縮できているはずです。
とくに学生なんかで「今は投げられないけど、他にやることいっぱいあるからね」と私に言われている選手も少なくないですが、極端に言ってしまえば、怪我している時は「通常の練習よりやることが多い」と思っておくのが正解です。
症例によってやるべきことが違うため、ここで内容を詳細にあげることは難しいですが、順序としては動きの悪いところの動きは良くして(可動域向上)、動かし方の再構築をして(動作改善)、復帰しても負荷に耐えられる筋力に戻す(強化)、ということを念頭に計画を立てています。
「強化」に関しては、どうしても競技の中でトレーニングする部分も出てくるので全てを補えるわけではありませんが、最低限、「練習に復帰できるレベルまで戻すこと」を念頭に進めています。
復帰まで時間がかかる、または復帰しても再発しやすいケース
①治療期間後にすぐ復帰してしまう(リハビリをしていない)
②リハビリ期間が短かすぎる
③リハビリ中の負荷が高すぎる
④復帰までのビジョンがない(選手の目標設定がない)
ざっと挙げるとこんなところでしょうか。
①は一般的な治療院に通っている場合に陥りやすいパターンです。「痛みが治まれば復帰できる」と考えている人がそうなりやすいです。
当院にも「〇〇接骨院で治療を受けて一旦良くなったんだけどまた痛くなってきて」という理由で来院される方が多くいらっしゃいます。
こういった方は「治療だけしてもダメなんだ」と理解している方々なので良いのですが、それに気づかず痛くなるたびに同じ治療を延々と受けている方は残念ですが、結局のところ何も変わりません。
②と③は一緒に起こりやすいパターンで、早く復帰させたいがために負荷を高く設定してトレーニングしてしまうケース。
いきなりウエイトを持たせてトレーニングする場合には起こりうるパターンです。
基本的に動作不良は自分の身体を自由に操れていない場合に見られるものですので、自分の身体も自由に動かせないのに重りを持ってトレーニングしても効率の良いトレーニングにはなりません。
当院のトレーニングでは、もっと掘り下げて、いきなり立った状態でトレーニングはせずに、重力の負荷を極力なくした寝た状態のトレーニングからスタートします。そして、意外と寝た状態ですら上手に動かせない方も少なくありません。
④はどちらかと言えば学生が陥りやすいパターンでしょうか。
当院には「〇月に大事な大会があるので、それに間に合わせたい」と来院される方が多いのでほとんどこのパターンの子はいませんが、「親に連れられて来ました」といった受け身の子の場合には、トレーニングを処方しても自宅でやらないケースもありますので、本人の意識はかなり大切な部分なのではないかと思っています。
スポーツ障害を再発させないためのまとめ
・ケガをしたなら治療を受けただけではダメ(リハビリ・トレーニングまでちゃんとおこないましょう)
・ケガをしているからこそやるべきことがたくさんある(治療と一緒にケガをした理由を消さなければならない)
・復帰を焦るよりも目の前の問題をひとつずつ解決する(早く治そうと考えるのは本人ではなく治療家の方で良い)
・復帰までのビジョンを明確に持つ(もう同じ思いをしたくない、いつまでに復帰したい等)
ランニング障害 , 施術について
2018年07月5日

宇都宮市JR岡本駅より徒歩5分。
可動域向上・動作改善・強化による症状の根本改善を目指した施術とパーソナルトレーニングを提供している鍼灸接骨院トレスです。
今回はシンスプリントに代表される「脛の内側の痛み」。
病院などでそのような診断を受けた方も少なくないとは思いますが、そこでの指導は「基本的に安静」というものが現実です。
もちろん、安静にするべき症状ではありますが、「どうしてシンスプリントになったのか?」ということを考えていくと、安静にしている間もやるべきことがたくさん出てきます。
病院で「安静にしなさい」と言われたからすべての運動を中止しているような方。
安静ばかりではいけません。ご自身の弱点を克服するべきタイミングなのかもしれません。
今回は、シンスプリントの患者さんの症例の中から、比較的多く見受けられる機能不全や動作不良についてご紹介します。
一度なってしまうと厄介なシンスプリントですが、繰り返さないために何をすべきか参考になればと思います。
シンスプリント・脛が痛くなった経緯を考える
基本的にシンスプリントはオーバーユーズ(使いすぎ)によるものです。
でも、「同じ練習メニューをこなしているあの子はシンスプリントじゃないのに私はシンスプリントになってしまった」のは何故でしょうか。
そこを考えていかないと、復帰した際に再発するリスクがあります。そして、シンスプリントの再発率は高いものです。
筋肉の柔軟性、関節の可動域、動かし方(運動制御)の問題などいろいろな原因がはらんでいます。
実際に確認すべきことは沢山ありますが、「こんな人は気をつけろ」的なところを挙げていきます。
シンスプリントになりやすい人
・硬い地面でのジャンプ動作が多い競技をしている人
・ダッシュ系の競技をしている人
・横にステップする動作が多い人(エアロビクスや打撃系の格闘技をする人)
・いわゆる偏平足の人(オーバープロネーションの人)
・足首の捻挫歴がある(内出血するレベルなら要注意)
・カカトをつけたまましゃがめない
・足の指が自由に動かせない などなど
ざっくり挙げてみましたが、当院にシンスプリントで来院される方の多くが該当しています。
シンスプリントになってしまったら
ちょっとでも脛の内側に違和感や痛みを感じたなら、すぐに医療機関や治療院を受診した方がよいでしょう。
痛みを我慢して運動を続けているともちろん悪化していきますし、一度悪化してしまうと治るまでに期間を要します。
ちゃんと診てくれる病院や治療院であれば、ちょっとの痛みや違和感であれば運動しながら治していく事は可能なはずです(ちゃんと診てくれる、が前提)。
一方で、足を着くだけで痛みを感じるなど、悪化してしまった場合は運動を中止することも検討しなければなりません。
その場合でも、やれること・やるべきことは沢山ありますので、そちらを優先して復帰後に再発しない体づくりをしていく期間と割り切ってしまうことも必要かと考えます。
シンスプリントになってしまった場合の患部へのアプローチとしては、はり治療や超音波治療器による物理療法、対象となる筋肉へのマッサージなどが一般的です。
ただし、これらも症状に対するアプローチ(対症療法)であり、復帰後の再発のリスクを考慮するとシンスプリントになってしまった原因へのアプローチが必要不可欠になります。
再発予防するなら治療以外に機能や動作に介入を
ダッシュや跳躍系のスポーツをする場合には股関節周辺の機能改善も必要になることもありますし、捻挫歴などがあり足部に問題があれば、そこのトレーニングも必要です。
シンスプリントなど、特にオーバーユーズでの障害では、治療以外に運動機能や動作改善に介入する必要があります。
そしてそのことが再発のリスクを軽減してくれます。
最後に、運動機能への介入例として足指の運動の動画を上げておきます。
偏平足やオーバープロネーションといった足部の問題を抱えている場合には積極的に取り入れてみてください。
やりかたの詳細は鍼灸接骨院トレスにご相談ください。