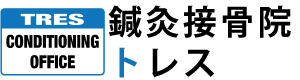-

長距離競技のサイクリストにもウエイトトレーニングを勧める理由
今回の内容は、サイクリストにもウエイトトレーニングをやってもらいたい理由を理詰めでつらつらと。 私の立場は、治療系のトレーナーですので、基本的にはトレーニングをする理由は「怪我からの復帰」や「怪我の予防」となりますが、パフォーマンスアップ... -

加齢による膝の痛みのおススメの改善法を紹介します
年齢とともに擦り減ってしまう膝の軟骨や半月板。そのせいで変形性膝関節症と診断されるかもしれません。 膝が痛くて病院に行くと先生に「年だから仕方ない」と言われ、憤って来院される方もいらっしゃいます。 不平や不満を愚痴ってもらってそれを聞くの... -

ジムでのスクワットで腰痛・膝痛が起きる原因は?予防方法を解説
昨今の健康志向のためか、以前より運動習慣のある方が増えてきています。 巷では24時間営業のジムが乱立されたり、短期間でダイエットをさせるジムなども流行っているようです。 どんな理由があろうと、運動習慣が身に付くのは良いことですので大歓迎です... -

繰り返す野球肩・野球肘の治療とトレーニングで必要な過程・期間
今回は繰り返す野球肩・野球肘の治療とトレーニングで必要な過程・期間について解説します。 野球肩や野球肘の診断を受けて投球制限(または禁止)を一定期間おこない復帰したものの、また同じ場所に痛みが出てきてしまったケースは多々あります。 思い起... -

【症例紹介】様々な医療機関の処置しなかった2年続いた野球肩
今回は2年続いた野球肩の改善事例をご紹介します。 先日来院された野球少年。中学1年時から肩の痛みに悩まされ、病院や接骨院を転々とするも快方に至らず、結果としてイップスのような症状も出てしまっていた2年以上経過した投球時の肩の痛みが主な悩みで... -

呼吸不足が腰痛・肩こりの原因になる理由を解説
今回のテーマは「呼吸」。これに関しては当院でも重要視しており、動作を改善するトレーニングを処方する前に改善しておきたい項目であります。 1日に2万回以上おこなわれる呼吸。慢性的に腰痛や肩こりなどを抱えている方で呼吸が浅い方が少なくありません... -

治療院で対応できる椎間板ヘルニアと対応できないヘルニアの違いは?そんな時はどうする?
当院には坐骨神経痛や椎間板ヘルニアを抱えた方が多くいらっしゃいます。 おかげで毎日程よい緊張感を持って仕事ができています。(治さなきゃプレッシャーでもある笑) 筋肉が原因の坐骨神経痛の場合には我々治療家でもすぐにアプローチできますが、ヘル... -

野球肩・水泳肩・サーブで肩が痛い etc 肩以外にある根本原因について
肩を痛めて病院などを受診して「肩甲骨の動きが悪いから肩を壊す」といったことを言われた方もいらっしゃると思います。 「しっかり肩甲骨を動かしているつもり」「そんなに肩甲骨硬くないと思うんだけどな…」と思いつつも言われた通り肩甲骨のストレッチ... -

バレーボールでの着地時の膝の痛みの原因は?正しい治療法は何?
バレーボールやバスケットボールなどの繰り返すジャンプ動作では膝の痛みがよく起こりますが、先日みさせていただいたケースについてご紹介します。 結果的には右膝に痛みがあったのですが、そこに至る経緯で左の股関節に問題があったケースです。 改めて... -

身体を壊さないために 野球における正しいランニングトレーニングとは
院長鈴木は元球児で、当時の練習などを思い返すことがあります。 今思えば何の根拠もないことをたくさんやっていたな、と思い出されます。 今回は、夏の大会に向けて球児たちのコンディショニング、とくにピッチャーが取り組む練習でのランニングについて...