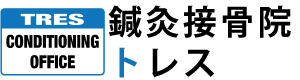以前某プロ野球選手が発症して何かと話題に挙がったハムストリングの肉離れ。
きちんとケアして復帰のタイミングを見極めないと、いろいろな問題が出てきますので、今回は鍼灸接骨院トレスが考えているハムストリングの肉離れの対処法から早期復帰までのプロセスをご紹介します。
ハムストリングとは
太ももの裏側にある複数の筋肉の総称です。
役割としては股関節の伸展や膝関節の屈曲などがメインとなっていますので、「走る・飛ぶ」などの動作で強い力を発揮します。
その動作中の強い収縮や、逆の強い伸長に耐え切れずブチっと切れてしまうのがハムストリングの肉離れです。
スポーツ選手だけでなく、一般の方が急に走ったりしても発症するケースがありますので、ハムストリングの基礎的状態だけでなく関連する場所の状態も良くしておきたいところです。
当院で多く遭遇するハムストリング肉離れ
当院では初発のハムストリング肉離れだけでなく、再発した肉離れや肉離れ歴があってそれ以来、調子を崩してしまっている方が多くいらっしゃいます(実は当院に来る方は前者よりも後者の方が多いです)。
再発や受傷歴があって調子が悪い場合には、間違いなくハムストリング単体の問題ではありませんので、グローバルに状態を確認していく必要があります。
また、ハムストリング肉離れの受傷歴があって他の場所に影響をもたらしているケースも少なくないため、既往歴としてのハムストリング肉離れも注意する必要があると感じています。
どこかに問題があり、ハムストリングにストレスがかかっているケース
スポーツ中にハムストリングを損傷する場合、単純な外力だけでなく他の場所との関係性を考慮する必要があります。
もちろん拮抗筋の伸長低下などもありますが、個人的に多く感じるのは「臀筋群」に問題があるケース(拮抗筋が伸びないから臀筋が使えないっていうのも一理あり)。
ハムストリングの中の大腿二頭筋は臀筋との筋連結があり股関節の動きと深く関わりを持っています。
お互いが協力して力を発揮できれば良いのですが、臀筋群がうまく作動していなくハムストリングばかり頑張ってしまっている状況をよく見かけます。
臀筋がうまく使えていない理由はアライメントやモーターコントロールなどいろいろなことが考えられますが、拮抗筋の伸長が得られている状態で、最終的に臀筋がもう少し使えていればハムストリングへの負担も減ったのではないか?と考えられるケースも少なくありません。
そういった意味では【可動域向上(ここでは拮抗筋の柔軟性)】だけではなく【動作改善(ここでは臀筋を使えるようにコレクティブすること)】もしていかなければならないことをご理解いただけると思います。
そして、スポーツをされている方であればハムストリングは受傷前に出せたであろうパワーまで戻さないと再受傷のリスクがあるため、復帰に向けては【強化】が必要となってきます。
スポーツ動作においてハムストリングの損傷も結構、厄介な症状です。
ハムストリングの受傷歴があって他の場所にストレスをかけているケース

当院でとにかく多いのがハムストリングを肉離れしてから腰痛で悩んでいるケースで、これはスポーツ習慣がある無いに関わらずよく遭遇します。
患者さん自身はハムストリングの肉離れが腰に影響しているとは思ってもみなかった場合が多いようですが、既往歴としてのハムストリング損傷は要注意です。
ハムストリングはいわゆる筋膜の連結で考えていくと腰の筋肉とも連結しているので、おおいに影響を与えるところでもあります。
しかも解剖学的にハムストリングの一部は骨盤(坐骨結節)に付着しているため、左右差も強調されてしまいます(両方同時に受傷するケースは少ない)ので、腰に負担がかかるのもご理解いただけると思います。
また、損傷後にハムストリングが元のように伸びなくなっている場合、その伸びないことが邪魔をして拮抗筋が頑張らなくてはならない環境になってしまいます(たとえばモモ上げのような動作)。
そういった影響もありますので、しっかりなおさないといけない症状でもあります。
ハムストリング損傷から復帰まで

一説によると、ハムストリングの肉離れは復帰後の早い時期に3割の確率で再負傷するとも言われています。
そうならないためには、リハビリの段階でしっかり負荷をかけておくことが必要になります。
再負傷する多くの原因は、リハビリでかけた負荷より練習で高い負荷をかけてしまった場合に起こります。
段階的に、①痛みのコントロール→②柔軟性の左右差をなくす→③ハムストリングへの負荷をかける→④競技復帰、という流れで復帰するのが良いでしょう(競技復帰しても当分は柔軟性とハムストリングへの負荷トレーニングは継続する必要があります)。
また、負傷中にかばった動作をすることによって動作不良を起こしているのなら、そこもしっかりクリアにしておきたいところです。
ちなみに、当院では多くの場合、鍼治療を併用しながら痛みをコントロールしつつ②と③の間に動作改善のコレクティブエクササイズを処方しています。
個人的には他の部位での肉離れよりも考慮することが多く、いろいろと厄介だなと感じています。
もし、ハムストリングを肉離れしてしまったのであれば、しっかり治すことをおススメします。
まとめ
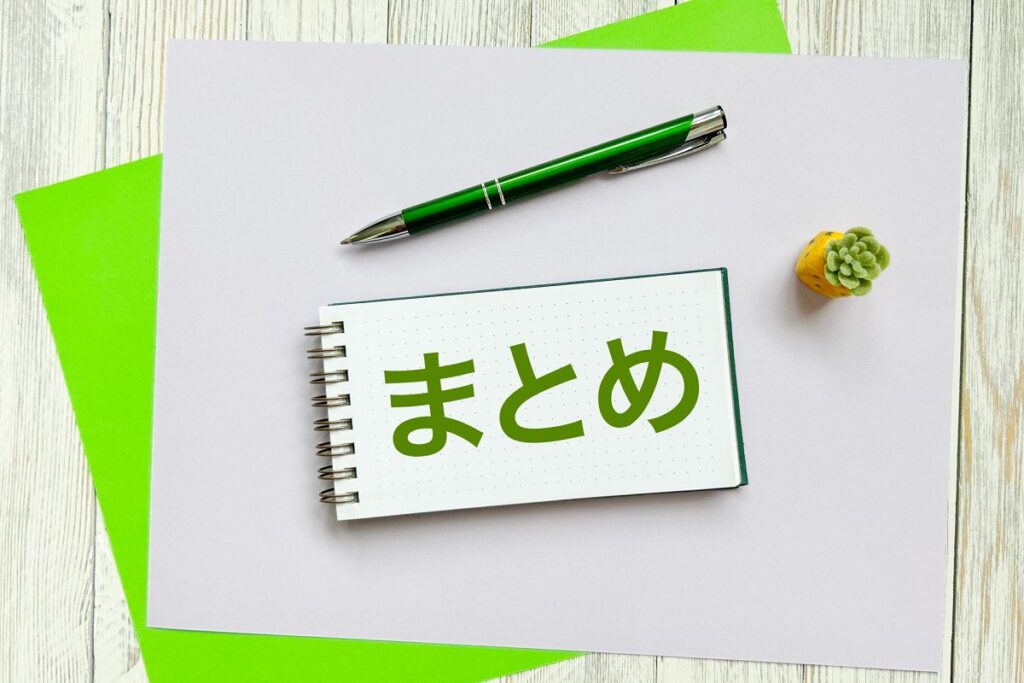
- 既往歴としてのハムストリング損傷は要注意(他の場所への影響力大)
- ハムストリングの肉離れは再発のリスクが高いので、しっかり治してから復帰する
- 練習で負荷をかける前に、リハビリ中にしっかり負荷をかけられる状態になっていないと復帰するのは危険
- 競技復帰後も一定期間、ハムストリングとそれに関連した場所のトレーニングは継続する
- もちろん、受傷期間中に代償動作が現れたら、その改善もする